あなたの会社では、採用面接のプロセスにどれくらい時間がかかっていますか?平均的に求職者の4分の1が面接の段階で離脱していると言われている中で、優秀な人材を採用するには、面接のプロセスを正しく行うことが極めて重要です。
【目次】
面接プロセスが原因で優秀な人材の採用機会を逃していませんか?
面接プロセスを効率的に進める方法
・人材エージェントを活用する
・理想的な面接の回数
・社内公募の選択肢を検討する
・面接のスケジュールを組む
・重複した質問は避ける
・Web面接と対面面接、どちらを選ぶべきか
・面接では適切な質問を
・面接プロセスにおける課題の提出
・面接プロセスにおけるフィードバックの提供
・最終選考〜口頭オファー〜契約
まとめ
面接プロセスが原因で優秀な人材の採用機会を逃していませんか?
多くの企業が採用プロセスに多くの時間を費やしているため、短期間で欠員を埋めることができないという問題に直面しています。
これらは、採用に課題を抱える企業によく見られる問題点です:
- 面接の回数が多すぎる
- 同じ内容で繰り返し面接を行なっている
- 給与に関する透明性が担保できていない
- フィードバックの提供に時間がかかりすぎている
これらはすべて、候補者にとっては赤信号となりえます。
面接を通じて、候補者が選考プロセスの進め方に疑問を持ったり、次のステップに進む意味を見出せなかったりした場合、選考途中での離脱につながりかねません。
面接プロセスを効率的に進める方法
人材エージェントを活用する
信頼できる人材エージェントとタッグを組むことで、採用担当者の時間と負担を軽減することが可能になります。
- 事前にスクリーニングされた、採用企業の価値観に合致する人材の候補者リストの提供
- 面接の日程調整
- 候補者に対するプロセス全体を通じたコーチング
- 候補者に対して常に最新情報を提供し、意欲を高める
- オファー交渉を管理し、採用企業が競争力ある給与を提示できるようにする
- 候補者が定着するまでオンボーディングに伴走
理想的な面接の回数
エグゼクティブ層の採用以外は2、3回の面接が理想的です。
- 若手から中堅管理職の場合は2回程度
- シニアリーダー採用の場合は、通常、経営幹部との面接があるため3回程度
社内公募の選択肢を検討する
外部からの採用を検討する前に、社内サーチを完了させましょう。求職者が時間と労力を費やして面接を受けた後(時には課題まで提出した後で)、企業が社内採用の選択肢を選んだことがわかると、採用C Xに対する不満につながります。社内公募の選択肢を最初に検討しておくことで、社外に求人広告を出す時間、ストレス、コストも節約できます。
面接のスケジュールを組む
面接担当者と採用責任者が合同で行うブリーフィングミーティングにて、関係者全員のスケジュールを抑えましょう。候補者のショートリストを作成するのには2週間程度あれば十分なはずです。Calendly(カレンドリー)のようなスケジューリングアプリを使えば、全員の予定がわかるため、複数のカレンダーをひとつひとつ確認する手間が省けます。さらに簡単なのは、AIを活用することです。
Goodtimeのようなツールは、スケジュール管理、リマインダー、面接の更新やフィードバックまでを自動化し、候補者のエンゲージメントを高めます。
重複した質問は避ける
堂々巡りの面接は避けましょう。候補者が答えをはぐらかしたり、何回も同じ例を使ったりするのを面接官が聞きたくないのと同じように、候補者も次の選考で別の関係者から同じ質問をされるのを望みません。
選考前に足並みを揃えることが、無駄のないプロセスの鍵となります。それが難しい場合は、 Gemini のようなLLMを活用してミーティングを書き起こし、チームで要約を共有できるようにするのも良いでしょう。
Web面接・対面面接、どちらを選ぶべきか
Web面接はコロナ禍より活発になっています。オンラインでの実施は効率的な一方で、対面面接と適切なバランスを保つ必要があります。Zoomで面接を通じて考え方や経験の合致を探ることで時間を節約しつつ、候補者にアクセシビリティの問題がない限り、対面でのフォローアップも行うべきです。オフィスを訪問してもらうことで、信頼関係を築き、納得してもらい、チームメンバーに会ったり、通勤時間を確認してもらったりすることができます。こうすることで、オンボーディング時の定着率を上げることにつながります。
また、アクセシビリティについて候補者と確認することは、正しい行動であると同時に、インクルーシブな風土を反映することでもあるため、双方にメリットがあります。
面接では適切な質問を
初回から適切な質問をすることで、プロセスを効果的かつ効率的なものにすることができます。技術的なスキルや経験と特定の状況にどう対応するかを評価するための質問を混ぜるのが良いアプローチです。職務に必要なスキルや経験は面接官も理解しているはずですが、AIを活用することで、質問プロセスを標準化し無意識のバイアスを避けるのに役立ちます。
GeminiやChatGPTに職務内容を入力し、10~15問の面接質問を作成させ、結果を絞り込んだり、さらに一歩進んで、候補者のプロフィールを参考にしつつ(候補者のデータプライバシーに留意することが求められます)、パーソナライズされた質問を生成したりすることもできるでしょう。
▼こちらの記事もおすすめ
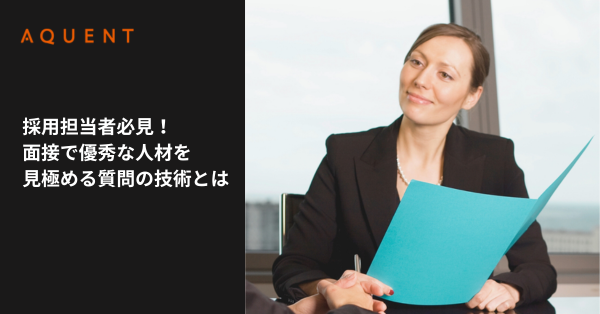
面接プロセスにおける課題の提出
課題選考は、クリエイティビティと実践的なスキルを測り、候補者のコミットメントを得るための理想的な方法です。ただし、適切に行わなければ、候補者の不満にもつながります。
非技術職の場合、1次面接の後に課題を設定し、2次面接で提出・プレゼンするのが一般的です。技術職の場合は、不正のリスクを減らすために、ライブテストが主流になってきています。
候補者の中には、課題選考を通じて有益なアイディアやクリエイティブを企業に無償で提供していると感じるケースもあるため、倫理的な観点から考え、企業の評判に影響が出ないよう注意することが大切です。
課題は簡潔にし、その目的や理由をきちんと説明する。特にクリエイティブ分野の課題は、どのように問題を解決し、どのような方法でそれに取り組むかを見るためにあります。結果は重要視されるべきではありません。
以前私がLinkedIn上で見かけた驚くべき選択肢は、候補者に所要時間分の報酬を支払うというものです。半日分の報酬を支払うことは採用企業のビジネスには大きな影響を及ぼしませんが、候補者にとっては大きなプラスとなりえます。とはいえ、このような例は多くないでしょう。
面接プロセスにおけるフィードバックの提供
定期的に、透明性のあるフィードバックを提供されることを候補者は望んでいます。候補者は仕事に応募した後、企業から返事がないことにはある程度の理解を示すかもしれませんが、面接に時間を費やしたのであれば、個別のフィードバックを提供することが重要です。
最終選考〜口頭オファー〜契約
面接プロセスにおいて、この段階にかかる時間は非常に重要です。オファーや契約内容を受け取るまでに何日も(場合によっては何週間も)待たされるのは、候補者にとって望ましくありません。熱い気持ちが冷めてしまう前に、採用担当者が実施できるチェックインの回数は限られています。
募集を出す前に給与(予算)の承認作業を済ませておき、「リファレンスチェック待ち」の状態で契約書の条件を提示することも、貴重な時間を節約することにつながります。人事部や採用チームは、バックエンドの契約プロセスを可能な限り合理化することを優先すべきです。
時には、すべてを正しく実行しても、遅れが生じることもあります。その場合は、候補者の期待値を管理する必要があります。透明性を保ち、現実的なタイムスケジュールを提示し、候補者のことを忘れていないことを示すために連絡を取る。このようなささやかな心遣いが、候補者の関心を惹きつけるのです。
まとめ
優秀な人材を採用するには、簡潔な面接の仕組みが不可欠です。
・始める前に社内のあらゆる選択肢を検討する
・最初の段階から給与に関する透明性を確保する
・誰が面接に出席する必要があるかを計画し、スケジュールを確保する
・迅速にフォローアップし、個別に建設的なフィードバックを与える
・ 人事や財務担当者とバックエンドの契約プロセスを合理化する
・テクノロジーやAIツールを取り入れる
テクノロジーを活用することは、今や重要な要素ではあるものの、人間にしかできないこと・人間が得意とすることとのバランスが必要です。事前に録音されたチャットボットとの面接が昨今のトレンドとして取り上げられています。候補者と関係性を構築し、候補者からビジネスに興味を持ってもらうためには、チャットボットが正しい選択肢であるとは、私は思いません。
AIは(現時点では)人間のように候補者と関係性を築いたり、彼らの感情的知性、カルチャーフィット、潜在能力を見抜いたりすることはできないため、雑務はAIに任せることでプロセスを効率化させつつ、実際の面接は人間が担当することをお勧めします。
【著者について】

Jimmy Sutton(ジミー・サットン)
オーストラリアとイギリスで9年間のリクルート経験を持つ。オーストラリアより、主にマーケティング&アナリティクスの分野で候補者やクライアントのサポートを行っている。



