インハウスデザイナーとは、事業会社に直接雇用され、自社の製品やサービスのデザインを専門に担当するデザイナーのこと。社内デザイナーとも呼ばれ、企業のブランド価値向上や事業成長をデザインの力でサポートすることを目的としています。
コストやブランド力の観点から、多くの企業が自社でデザイナーの採用を検討していますが、求める人材像や評価基準が曖昧なまま進めてしまい、後悔するケースが少なくありません。
そこで今回は、インハウスデザイナー採用で陥りがちな課題から、採用基準、育成・定着の具体策、企業ブランディングへの活用法まで、採用に役立つポイントを解説します。
【目次】
インハウスデザイナーとクライアントワークとの違い
・企業ブランドブランドの維持
・長期的プロジェクトの担当
企業がインハウスデザイナーを採用する具体的なメリット
・コスト削減が見込める
・ブランド統一が可能
・社内コミュニケーションが円滑
・迅速な対応が可能
優秀なインハウスデザイナーを見極めるための採用基準と評価ポイント
・ポートフォリオの充実度
・コミュニケーションスキル
・ブランド理解度
・問題解決能力
インハウスデザイナー採用に失敗しやすい企業の共通課題
・採用基準が不明確
・評価基準が不十分
・定着率が低い
インハウスデザイナーの採用後に実践すべき育成と定着ノウハウ
・定期的なフィードバック実施
・キャリアパスの明確化
・社内研修の実施
・モチベーション管理
・ワークライフバランスの維持
まとめ
インハウスデザイナーとクライアントワークとの違い

インハウスデザイナーは、クライアントから直接依頼を受けて業務を遂行するクライアントワーク型のデザイナーとは働き方が異なります。
ここでは、インハウスデザイナーの特徴的な役割について具体的に解説します。
企業ブランドの維持
クライアントワーク型は案件ごとにブランドが異なり、さまざまな業界・業種のクライアントのプロジェクトに関わるため、多様なデザインを経験できます。
それに対し、インハウスデザイナーは、企業のブランドイメージやガイドラインを深く理解し、日々の業務を通してその一貫性を保つ役割を担います。
例えば、社内外向けの資料や広告、ウェブサイト、パッケージデザインなど幅広い領域でブランドの統一感を守ります。
一貫性のあるデザインが顧客の信頼につながり、結果的に企業価値を高めることにも貢献するのです。
長期的プロジェクトの担当
インハウスデザイナーは、企業内で長期間にわたるプロジェクトを継続的に担当できる点が特徴です。クライアントワークの場合、案件が終わると関与も終了しますが、インハウスでは新商品の立ち上げやブランドリニューアル、年間プロモーションなど、長期ビジョンに基づいたプロジェクトをじっくり推進できます。
これにより、企業独自のノウハウやデザイン資産が蓄積され、継続的なブランド成長やマーケティング活動に活かされる土台作りが可能になります。
企業がインハウスデザイナーを採用する具体的なメリット

企業がインハウスデザイナーを採用することで得られるメリットは多岐にわたります。
ここでは、採用を検討する際に特に押さえておきたい具体的なメリットについて解説します。
コスト削減が見込める
インハウスデザイナーを採用することで、外部委託にかかるデザイン費用を抑えることができます。都度発生する制作費や修正費用が不要になり、予算計画が立てやすくなります。内製化によって短期的には人件費が発生しますが、長期的にはコストパフォーマンスを高めることが可能です。頻繁にデザイン案件が発生する企業ほど、この効果を実感しやすいでしょう。
ブランド統一が可能
社内に専任のデザイナーがいることで、ロゴや資料、広告などすべてのクリエイティブに一貫性を持たせることができます。ブランドガイドラインの維持や、企業イメージの統一された発信がしやすくなります。外部委託と比較して、企業独自のトーンや世界観を継続的に反映できる点は、長期的なブランディング戦略にとって重要な要素です。
社内コミュニケーションが円滑
インハウスデザイナーがいることで、企画や営業、マーケティング担当者との連携が密になります。社内の関係者同士で気軽に打ち合わせやアイデアのすり合わせができるため、認識のズレやコミュニケーションロスを防ぐことができ、デザイン意図を直接伝えたり、細かな調整もスムーズに進められる点が大きな利点です。
迅速な対応が可能
緊急のデザイン修正や突発的な業務依頼にも、社内にデザイナーがいることでスピーディーに対応できます。外部委託の場合、納期やコミュニケーションに時間がかかることがありますが、インハウスなら依頼から制作までのリードタイムを大幅に短縮可能です。新しい施策や変更が多い業界では、この柔軟性が大きな強みとなります。
優秀なインハウスデザイナーを見極めるための採用基準と評価ポイント

インハウスデザイナーの採用では、企業のブランド価値を高めるために、専門的なスキルだけでなく組織内で活躍できる適性も重視する必要があります。ここでは、それぞれの評価ポイントについて詳しく解説します。
ポートフォリオの充実度
ポートフォリオは、応募者がこれまでどのようなプロジェクトを手掛けてきたかを判断するための最も重要な資料です。インハウスデザイナーの場合、企業やブランドの目的に沿ったアウトプットができているかが最大の評価ポイントとなります。
また、プロジェクトごとにどのような役割を担ったのか、作品の意図や工夫した点が明確に説明されているかも評価基準となります。応募者本人の関与度や思考プロセスが具体的に示されているポートフォリオは、実務での活躍をイメージしやすくなります。
コミュニケーションスキル
インハウスデザイナーは、他部門のメンバーと協力しながら業務を進める機会が多い職種です。そのため、単独で優れた成果を出すだけでなく、チーム内での円滑なコミュニケーションや共同作業への貢献度も重要な評価ポイントとなります。
面接時には、過去にチームで取り組んだエピソードや、他メンバーとの役割分担、コミュニケーション事例、意見調整の経験について具体的に質問することで、応募者の協調性やリーダーシップの有無を把握できます。
ブランド理解度
企業のブランディングを担うインハウスデザイナーには、自社のブランドアイデンティティやターゲット層への深い理解が求められます。単なるデザインスキルだけでなく、ブランドの価値を的確に表現・提案できるかが採用の大きな判断基準です。
ブランドガイドラインへの準拠だけでなく、ブランドの価値をより効果的に伝えるための提案力があるかも確認が必要です。評価の際には、応募者がこれまでにどのような形でブランド理解を深め、制作に反映してきたか、その具体的な事例や思考プロセスをヒアリングすることが有効です。
問題解決能力
インハウスデザイナーは、限られたリソースやタイトなスケジュール、部門間の意見の違いなど、様々な課題に直面します。こうした状況下でも、柔軟に対応し最適な解決策を導き出せる力が不可欠です。採用時には、過去のトラブル対応や課題解決の具体例を質問し、どのように状況を分析し、どんなアクションを取ったのかを確認することで、実践力や適応力を測ることができます。
▼こちらの記事もおすすめ
採用担当者必見!面接で優秀な人材を見極める質問の技術とは
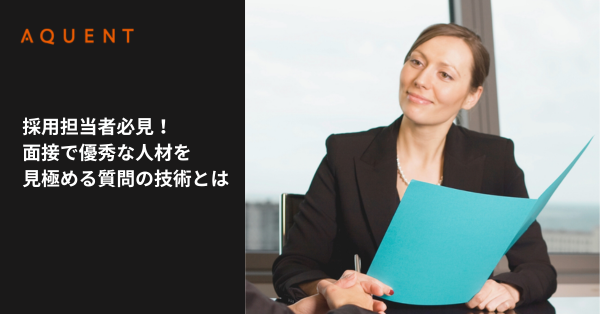
インハウスデザイナー採用に失敗しやすい企業の共通課題
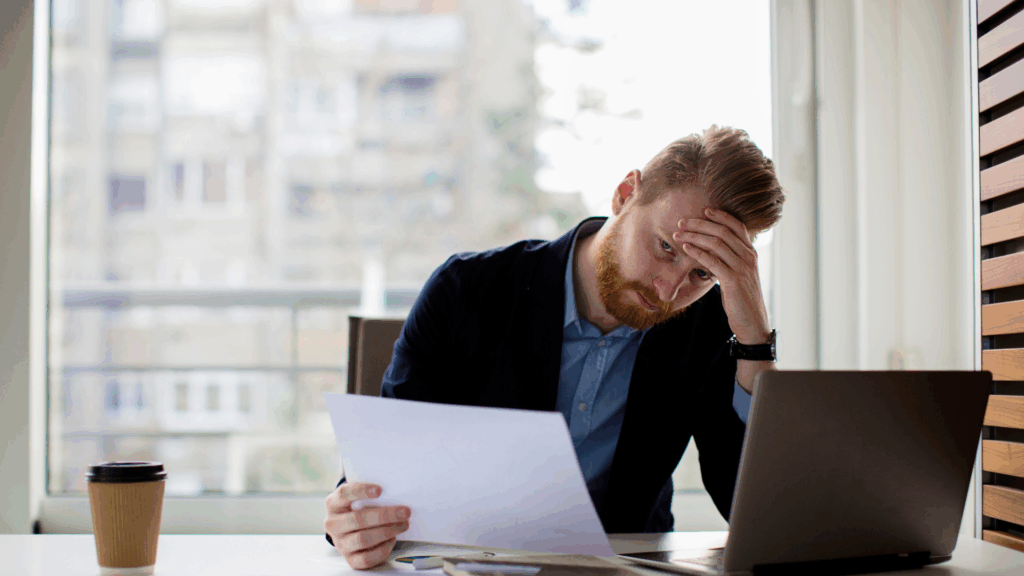
インハウスデザイナーの採用に取り組む企業が直面しやすい課題には、明確な採用基準や評価基準の不備、そして人材の定着率の低さが挙げられます。
ここでは、それぞれの課題が具体的にどのようなものかを整理し、採用活動の見直しの参考となるポイントを解説します。
採用基準が不明確
インハウスデザイナーの採用で最初につまずきやすいのが、求めるスキルや経験、業務範囲の明確化が十分でない点です。自社に必要なデザインの方向性やレベル感を定義できていないと、応募者のポートフォリオやスキルセットを適切に評価できません。
また、クリエイティブ領域に不慣れな担当者は「何となく良さそう」といった曖昧な基準で選考を進めてしまうため、入社後のミスマッチや期待外れを招くリスクが高まります。採用活動を始める前に、自社で本当に求めるデザイナー像を具体的に描くことが重要です。
評価基準が不十分
採用後の評価基準が曖昧な場合、デザイナー本人も自身の成長や成果を実感しにくくなります。特に、成果物の評価や業務プロセスの可視化ができていないと、他部門とのコミュニケーションもすれ違いが生じがちです。クリエイティブ職の評価には、単なる納期や件数だけでなく、ブランドへの貢献度や提案力なども含めて多角的に見る視点が不可欠です。評価体制の整備が不十分だと、モチベーション低下や早期離職につながるため注意が必要です。
定着率が低い
せっかく採用したインハウスデザイナーが早期に退職してしまうケースも珍しくありません。これは、デザイナーが組織内で孤立しやすく、キャリアパスや成長機会の提示が不十分な場合に多く見られます。また、クリエイティブな発想や提案が受け入れられにくい社風だと、やりがいを感じにくくなることも要因となります。環境面の工夫や、他部門との連携強化、適切なフィードバックの仕組みを作ることで、定着率向上につなげることができます。
インハウスデザイナーの採用後に実践すべき育成と定着ノウハウ

インハウスデザイナーを採用した後、企業が直面しやすいのが「育成」と「定着」の課題です。採用時のマッチングだけでなく、入社後の育成施策や働く環境づくりが非常に重要となります。
ここでは、採用後に実践すべき育成について具体的な方法を解説します。
定期的なフィードバック実施
デザイナーは成果物が目に見えやすいため、定期的なフィードバックが育成に大きな影響を与えます。プロジェクトごとに先輩や同僚が意見を伝えると、成長の方向性を明確にできるでしょう。
特に、評価基準が曖昧になりやすいデザイン領域では、具体的な良かった点や改善点を伝えることが重要です。これにより、自己評価だけに頼らず、客観的な視点でスキルアップできる環境が整います。フィードバックの場は、業務改善だけでなく、コミュニケーションを深める機会にもなるでしょう。
キャリアパスの明確化
インハウスデザイナーが長く活躍するためには、将来像を描ける環境が欠かせません。キャリアパスを明示することで、目指すべき目標や必要なスキルがクリアになるでしょう。
例えば、「リーダー職」「専門性強化」「新規事業に携わる」など、複数の選択肢を提示する企業もあります。キャリアアップのイメージが持てることで、デザイナー自身の成長意欲を引き出しやすくなります。採用時や定期面談でキャリアの方向性を話し合うことも有効です。
社内研修の実施
社内研修は、デザインスキルだけでなく、ブランディングや業界知識の強化にも役立ちます。外部講師を招いたワークショップや、他部署との交流型研修を取り入れると、視野が広がり企業理解も深まります。また、最新のツールやトレンドを学ぶ機会を用意することで、デザイナーの専門性を継続的に高めることが可能です。研修内容は現場の課題やデザイナーの希望に合わせてカスタマイズすることがポイントです。
モチベーション管理
インハウスデザイナーのモチベーションを維持するには、日々の声かけや成果の可視化が効果的です。具体的には、プロジェクトの成功事例を社内で共有したり、クリエイティブなアイデアを評価する場を設けたりする方法があります。加えて、業務の幅を広げるチャレンジ機会や、自己成長を実感できるタスクの付与も重要です。モチベーションが高まれば、定着率向上にもつながります。企業文化としてクリエイティブを尊重する姿勢を示すことが大切です。
ワークライフバランスの維持
クリエイティブ職は業務量や納期による負担が大きくなりやすいため、ワークライフバランスに配慮することが大切です。例えば、残業の抑制や在宅勤務の導入、フレックスタイム制度など柔軟な働き方を整備することが効果的でしょう。
健康管理やメンタルケアのサポート体制も、長期的な活躍を支える大切な要素。デザイナーが安心して働ける環境づくりが、結果としてクリエイティブの質向上や定着につながります。
まとめ
インハウスデザイナーの採用は、単なるデザインリソースの強化にとどまらず、企業ブランディングや業務効率化、社内コミュニケーションの活性化といった多面的な効果が期待できる でしょう。
しかし、採用基準の曖昧さや評価体制の不備、定着率の低さは、多くの企業に共通する課題点。採用を成功させるためには、明確な評価基準の策定、ブランド理解度やチームワーク力を重視した選考、入社後の育成が不可欠です。
今回ご紹介したポイントを押さえ、インハウスデザイナーの力を活用することで、企業ののブランド価値向上と組織力強化につなげていきましょう。
採用にお悩みの際は、エイクエントのエージェントへ お気軽にご相談ください。



